
2012年に個人向けの名刺管理アプリとして誕生した「Eight」は、名刺管理にとどまらず、キャリアや人脈の可視化など、ビジネスパーソンの可能性を広げるサービスへと進化を続けています。新機能の拡充が続き、さらなる成長に向けて、サービス基盤の再構築にも挑戦しています。13年間蓄積されてきたコードと設計を見直しながら、未来の価値提供に向けて開発体制を再編成しているのです。創業メンバーでありEightの事業部長を務める塩見賢治と、技術本部 Eight Engineering Unitのマネジャーを務める間瀬哲也に、サービスと組織の現在地、そしてこれからについて話を聞きました。
PROFILE

間瀬 哲也Tetsuya Mase
技術本部 Eight Engineering Unit GrM
2010年9月にSansanへ入社し、インフラエンジニア第一号として、当初はプロダクトから社内まですべてのサーバ、ネットワークの管理・運用に従事。名刺アプリ「Eight」のインフラの設計・構築の責任者を経て、現在は Eight のプロダクト開発や SRE などのエンジニア組織のマネジャーとして組織とプロダクトの成長に向き合う。

塩見 賢治Kenji Shiomi
取締役/執行役員/Eight事業部 事業部長
株式会社物産システムインテグレーション(現・三井情報株式会社)で、大手携帯キャリア向けのメールシステムの設計・開発責任者などを務めた後、2007年にSansan株式会社を共同創業し、2012年から名刺アプリ「Eight」の事業責任者を務める。現在は、技術本部の本部長として技術戦略や組織強化を指揮。
名刺文化の先にある未来を描く
塩見さんはSansanの創業メンバーであり、「Eight」の立ち上げにも携わっています。提供を開始した背景から聞かせてください。
塩見:創業前の話ですが2000年から約2年間、シリコンバレーに滞在していました。現地で多くの起業家と会ったのですが、実際に話してみると、意外にも普通の人たちだと感じることが多かったのです。つまり、彼らは決してスーパーマンのような存在ではなく、私たちと同じような人たち。自分も必死に努力すれば、同じように世の中を変えられるはずだと考えました。
その後、「紙の名刺には複数の課題があるから、いずれなくなる世界が来るだろう」という思いのもと、Sansanを創業して営業DXサービス「Sansan」の提供を始めました。数年ほど経った頃、サービスが人々のニーズに合っている手応えがあった一方で、「世の中を変えるには、法人向けのアプローチだけでは足りないかもしれない」という感覚も覚えました。
もしかしたら、私たちの事業が広がる前に、他社のビジネスネットワークサービスが流行してしまうかもしれない。そうした危機感から、「一般消費者向けのサービスも立ち上げよう」と始めたのが「Eight」です。まずは多くの人に使ってもらうため、完全無料で提供を開始しました。
その後、Eight事業としては2024年5月期に初めて一年間を通じて黒字化を達成しました。そんな中でも、なぜ事業を継続する意思を貫けたのでしょうか?
塩見:確かに収益という面では苦労が続きましたが、「Eight」のユーザー数の成長は一度も止まったことがありませんでした。新型コロナウイルス感染症の流行という困難があっても、13年間にわたりユーザー数は伸び続けてきました。だからこそ、「私たちが思い描いていた未来はきっと来る」と信じ続けられたのです。
現在「Eight」は、単なる名刺アプリではなく、ビジネスネットワークサービスとしての役割も持っています。ユーザーは「Eight」で相手のプロフィールを見れば「この人はどんな活動をしているのか、どんな業界に深い知見を持っているか」といったことがわかり、その情報によって新たなビジネスが生まれたりキャリアチェンジのきっかけになったりするからです。その結果「Eight」を通じて「人脈とはスキルの一部である」という概念を広められたと感じています。
開発組織成長のために
アクセルを踏み込むフェーズ
「Eight」の開発組織において、今後の伸びしろはどのような点にありますか?
間瀬:直近数年は、Eight事業の黒字化を目指して複数の施策を実施してきました。その影響で採用人数を絞っていたのですが、売上も順調に伸びてきたため、今後は採用を強化していこうと考えています。また、スピードを優先して開発を進めてきた経緯や、もともと存在しなかった概念を後から追加した部分もあるため、機能によっては設計がややいびつになっているところもあります。そうした箇所には、再設計などの対応が必要です。新機能の開発とリファクタリング(既存システムの再設計・整理)の両方が求められる、私たちにとって面白いフェーズに入ってきたと感じています。
具体的には、どのような方法で新機能開発とリファクタリングのバランスを取っているのでしょうか?
間瀬:2025年3月から開発体制を変更し、新機能開発を担うチームと、生産性向上やシステム基盤の改善を担うチームをそれぞれ設けました。それぞれのチームに裁量を与えながら、開発を進めているところです。
この記事は、おそらく働くことを検討しているエンジニアにも届くはずです。他社と比較して、「Eight」のサービスや開発組織の特徴はどのような点にあるでしょうか?
間瀬:開発組織として一番の強みは、ビジネスサイドとの距離が非常に近いことです。まるで隣で仕事をしているかのような距離感で、お互いに気軽に相談し合える関係性があります。また、塩見さんも話していたように、サービス自体のユニークさや社会的意義も大きな特徴です。単なる名刺管理ではなく、名刺を起点として「ビジネスパーソンがどのように生きてきたか」までを表現できるサービスだからです。
塩見:「Eight」では、名刺管理にとどまらず、さまざまな事業を展開しています。例えば、中小企業向け名刺管理サービス「Eight Team」や採用支援サービス「Eight Career Design」、さらには「Climbers」や「Startup JAPAN EXPO」などのビジネスイベントも開催しています。デジタル空間だけでなく、リアルな場においても変革を促す施策を進めている点は、Eight事業の特徴的な面白いポイントです。
実際、エンジニア自身がイベントに足を運び、ユーザーの方々と直接対話する機会もあり、プロダクトに対する反応を肌で感じられる貴重な体験です。さらに、ブースを回る中でクライアント企業(出展社)の方々とコミュニケーションを取ることもあり、アプリの開発にとどまらない広い視野が養われます。
「Eight」ならば世の中を変えられる
「Eight」が目指す世界観が実現されることで、社会やビジネスのあり方にどのような影響を与えると考えていますか?
塩見:自分自身の人脈をたどったり、有効活用したりしながらビジネスを始めるという流れが、より一般的になっていくはずです。
もう一つは、必要な人を必要なタイミングで探せるようになることです。「こういうことをやりたい」と思ったときに、マッチするスキルや経歴を持った最適な人と出会い、商談や協業につなげる。そんな未来が実現できると考えています。何かを始める際に、まず「Eight」で調べて、そこからアクションを起こすような、効率的な世界になるといいですね。
さらに言えば、「Eight」を個人認証の手段として使うことも視野に入れています。たとえば、ビジネスイベントなどの認証が必要な場面で、運転免許証や保険証のような個人情報が多く記載された書類を第三者に見せるのは抵抗がありますよね。そうしたケースにおいて、個人情報を過度に開示することなく、十分な身分証明として活用できる仕組みになればと考えています。
また、紙の名刺は、その時点での経歴のスナップショットにすぎません。一方、「Eight」の良いところは、情報が常にアップデートされながら履歴としても残っていく点です。「Eight」で名刺情報を受け取っておけば、時間が経ってもその人の最新情報が常にわかる。勤務先や所属が変わっても、すぐに把握できる未来がやってくると思います。
2025年には、非ユーザーともQRコードで名刺交換ができる新機能をリリースしました。スマートフォンのカメラで読み取るだけで、Eightのアカウントを持っていない相手にもスムーズにデジタル名刺を渡すことができます。このように、誰とでもスピーディに出会いをつなげられる体験が、ビジネスの効率と可能性を大きく広げています。
最後に、これから「Eight」の開発組織に加わるエンジニアに向けてメッセージをお願いします。
間瀬:エンジニアとして設計や開発のスキルは求めます。ただ、それだけでなく「サービスをどう成長させ、どう世界を変えていくのか」という視点を大切にできる方に加わってほしいです。名刺のデジタル化から始まった「Eight」は、個人向けのBtoCだけでなく、企業向けBtoBの活用も含め、ビジネス全体に新しい価値をもたらすポテンシャルを秘めています。「すべてのビジネスパーソンに使ってもらえるサービス」を目指しているので、既存の名刺文化にとらわれない価値創出を追求していきましょう。
塩見:積極的にエンジニアの採用を進めていますが、極端に大きな組織にするつもりはありません。できるだけ少数精鋭で、スキルの高いメンバーを集めて、エッジの効いたサービスを展開していきたいと考えています。組織はコンパクトですが、扱っているユーザー数やデータは膨大です。だからこそ、一人ひとりのミッションも大きいですし、そうした環境にやりがいを感じてくれる人に来てもらいたいですね。
それから、「世の中を変えたい」という気持ちをエンジニアにも持っていてほしいです。私たちもサービスと13年間向き合ってきて、ようやく「プロダクトで世の中を変えられるかもしれない」というフェーズに来ています。13年間も続いて、かつ事業としても成功の見込みがあるサービスは、そう多くありません。一緒に貴重な経験をしながら、新しい世界をつくっていけたら嬉しいですね。
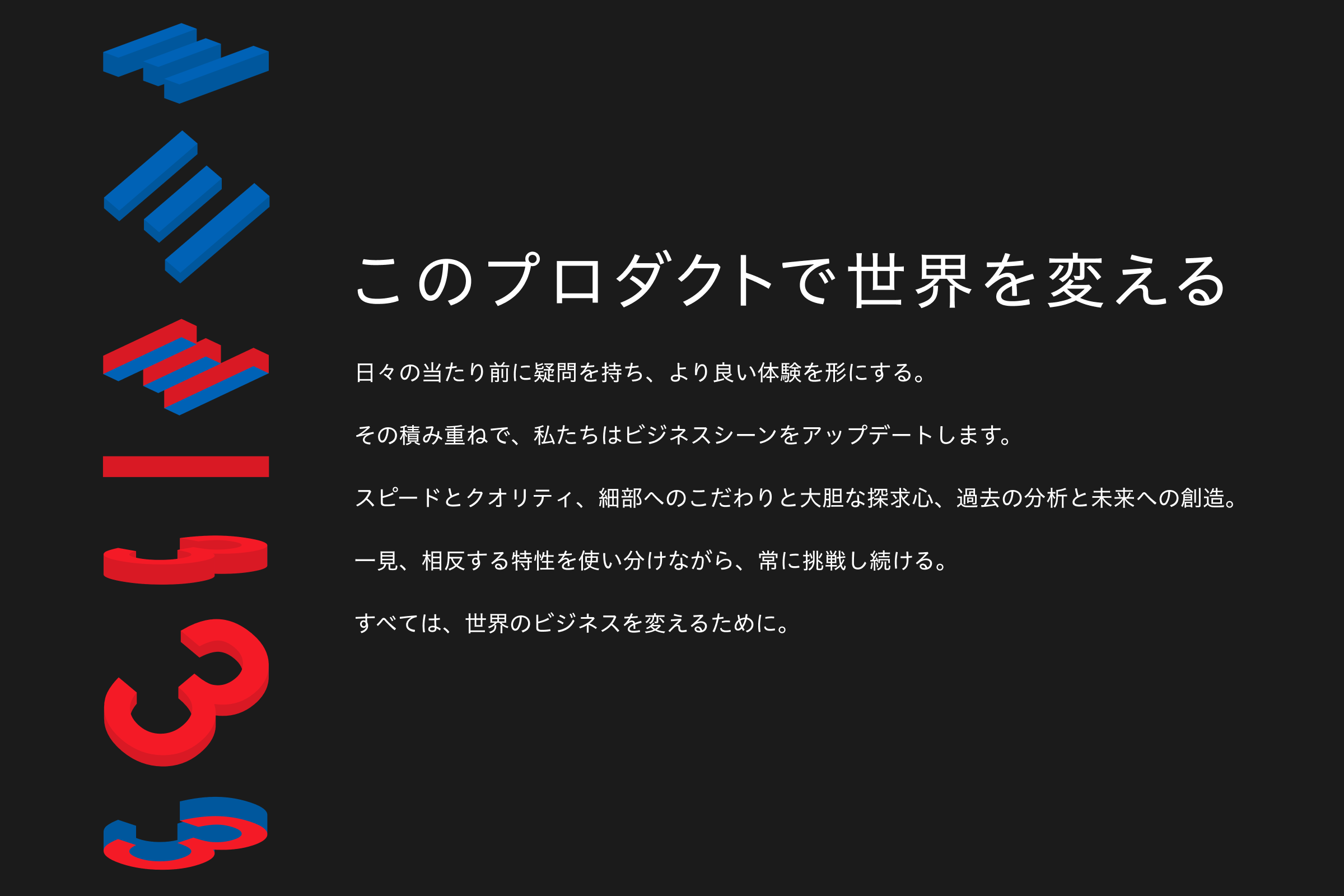
塩見:実は昨年、技術本部として「このプロダクトで世界を変える」というスローガンを掲げました。これは「Eight」だけに限らず、私たちが提供するすべてのサービスを通じて世の中に変化を起こす、という意志の表れです。名刺文化を変える先にはより大きな世界の変化があり、私たちはその挑戦を技術本部のメンバーと一緒にやっていきたいと思っています。
開発現場のリアルに迫るインタビューも公開中
本記事では「Eight」の開発組織全体の現在地と今後の展望をお伝えしましたが、実際の現場ではどのようなメンバーが、どんな想いで開発に取り組んでいるのでしょうか?新機能開発、技術改善、イベント体験の向上。それぞれ異なる役割を担う3つのチームに迫ったこちらの記事も、ぜひあわせてご覧ください。




