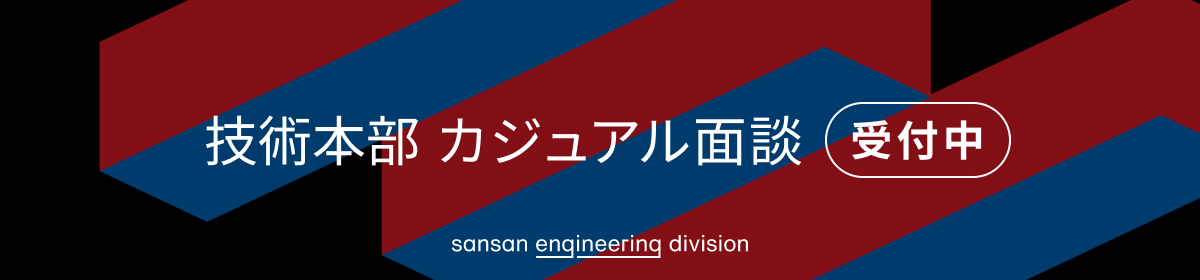「Contract One」は、あらゆる契約書を正確に理解しデータ化することで、クラウド上での一元管理を可能とする契約データベースです。2024年にPMF(Product Market Fit:製品が顧客に受け入れられ、市場に適合した状態)を達成し、さらなる事業成長を目指しています。このプロダクトの開発を支えるのが、Sansan株式会社に新卒入社後、インボイス管理サービス「Bill One」や受注管理サービス「Order One」を経て、現在「Contract One」に関わっているエンジニアの山邊直也。開発の魅力や今後のビジョンなどを聞きました。
PROFILE

山邊 直也Naoya Yamabe
技術本部 Strategic Products Engineering Unit Contract One Devグループ
2019年夏にSansan株式会社でインターンを経験した後、翌年2月に高専を4年次で中退し、Sansanへ入社。入社後はローンチ前であったインボイス管理サービス「Bill One」の開発に従事。2023年7月から受注管理サービス「Order One」の開発を経て、2024年7月から現在まで契約データベース「Contract One」に従事。Webエンジニアとしてプロダクトの機能開発を通じてプロダクトの価値向上に向き合っている。
「Contract One」の抱える課題に惹かれた
まずは、Sansanでのキャリアの変遷についてお聞かせください。
Sansanに新卒で入社し、まずは「Bill One」の開発に参画しました。当時のチームはまだ小規模で、私は社員として4人目のエンジニアでした。そこから開発組織の規模が80人ほどになるまで在籍し、主に初期フェーズでは「属人的だがスピード感のある開発」を、後期フェーズでは「組織をうまく機能させる仕組みづくり」を経験しました。
「Bill One」が事業として成長したため、また新規プロダクトの立ち上げに関わりたいと考え、「Order One」の開発チームに異動しました。ここでも、小規模な組織でのスピーディーな開発に取り組みました。しかし、その後サービス終了が決定。次のキャリアを考えるために社内の複数のメンバーと会話をしました。
そうしたメンバーとの会話の中で、「Contract One」が抱える課題について話を聞く機会がありました。事業成長のフェーズにある「Contract One」では、技術面・組織面の両方とも複数の課題があります。たとえば、技術面においては「改修の難易度が高いコードがある」「ドメインモデリングができていない」「手作業の運用作業も残っている」などです。そして、組織面において「組織を活性化したい」という課題があったことは、自分にとって魅力的でした。
私はこれまで複数の小規模のチームでチームビルディングを経験し、周りへ与える影響を他のメンバーからも評価してもらうことが多かったのですが、プロダクト組織全体を活性化した経験はありませんでした。チームビルディングのスキルをもっと伸ばしたいと考えていたため、「Contract One」ならば良い挑戦ができると感じました。
「Contract One」のプロダクトや組織の特性はどのような点にありますか?
PMFを達成したとはいえ、プロダクトはまだ成長期にあります。さらに、世の中には契約書を扱う競合サービスが複数存在するため、「差別化のために『Contract One』特有の強みをどう生み出していくか」「競合サービスにある機能を『Contract One』にも実装すべきか」など、考えるべきことは山ほどあります。開発リソースは限られているため、これらを取捨選択しながらプロジェクトを進める必要があります。
また、組織の成長を間近で経験できます。「Contract One」はよりクロスファンクショナルなチームを目指しており、エンジニアが営業やカスタマーサクセスなど他職種のメンバーと密接に関わることができます。これらの職種のメンバーから間接的にユーザーの声を聞けますし、またイベントのブースにエンジニア自身が立ち、ユーザーと直接交流できる機会もあります。
柔軟性が高く、Sansan固有の強みを活かせる開発組織
「Contract One」の開発スタイルの特徴がよく表れている事例はありますか?
Sansanが提供しているほかのプロダクトと比較すると、AIを活用した機能開発を積極的に進めている点が特徴です。最近では「拡張項目のAI自動入力」を実装しました。
契約書には、賃貸借契約では「物件名」、やライセンス契約では「作品名」など、事業内容に応じた重要な項目が記載されています。ユーザーがこれらの項目を確認しやすくするには、契約書ごとに該当箇所を抽出し、一覧化する必要があります。しかし、手作業では手間がかかるうえ、ミスが発生する可能性もあるのが懸念です。そこで、あらかじめユーザーが設定した項目を契約書本文からAIが自動で抽出する「拡張項目のAI自動入力」機能を開発しました。
また、私たちのチームでは、営業やカスタマーサクセスのメンバーが「お客様からこんな声をいただいた」といったフィードバックをエンジニアに共有する仕組みがあります。「拡張項目のAI自動入力」に関しても、ポジティブな反応が多く寄せられており、ユーザーの意見を直接知ることができています。
現在、「Contract One」ではエンジニア採用を強化していますよね。優秀なエンジニアの方々は、Sansanだけでなく、小規模なスタートアップ企業も転職先の候補にすることも多いです。そうした他の企業と比べて、「Contract One」固有の良さは何にありますか?
まず、「Contract One」はSansanという企業の基盤の上にあり、腰を据えて挑戦できる環境が整っている点が大きな魅力です。たとえば、短期的な利益にとらわれず、中長期的な視点でプロダクトの価値を高めるための開発ができますし、必要に応じてある程度の投資を伴う施策にもチャレンジできる体制があります。
また、社内に蓄積された豊富な技術的知見にもアクセスしやすく、何かに挑戦するときに「前例」や「知恵」を頼れるというのは、大きな安心感につながっています。
それから、Sansanの事業のコアには「データ化の技術」があり、「Contract One」の契約書の自動ひも付け機能などに活かされています。この技術によって、他社との差別化につながる機能の開発も容易になります。
エンジニアに与えられる裁量の面では、セキュリティ上の問題がない範囲であれば、非常に自由度が高いです。たとえば、最近ではソフトウェア開発におけるタスクを自動化・効率化する、ClineやDevinなどのAIエージェントが発展しています。チームに導入したいと相談したところ、すぐに予算が確保され、その日から試せる環境が整いました。
プロダクト開発においても、デザイナーやプロダクトマネジャーと協調して働く文化があります。それぞれが自身の強みを活かしながら開発を進める中で、エンジニアも意思決定に関与でき、気軽に相談できる雰囲気があるのも魅力です。
視野を広げて、プロダクトへの要求を超える
どのようなタイプのエンジニアが活躍できますか?
まず、意思決定ができることが重要です。「Contract One」のプロダクト組織は、メンバー同士のさまざまな意見が飛び交う環境で、良い意味で「ごった煮」感があると言えます。事業について不確実な要素が多い中で、周囲としっかりコミュニケーションを取りながら、最終的には自分で方針を決めて仕事を進めるオーナーシップが求められます。また、新しいことに積極的に挑戦する姿勢も重要です。発想力や行動力のある人が活躍しやすい環境だと思います。
加えて、私たちの開発組織は「すごい人だけがリーダーをやる」のではなく、「みんながリーダーというロールを担う」という考え方が根付いており、立候補制に近い形でジュニア層のメンバーもチームリーダーとして活躍しています。自然とリーダーシップを磨ける環境があるため、チームを率いる経験を積みたい方には多くのチャンスがあります。
実際の働き方やチームの雰囲気については、noteで紹介された高野の1日密着記事もぜひご覧ください。チームカルチャーや出社のメリットなどが具体的に描かれています。
それから、ビジネス的な視点を持つ必要がある一方で、技術を単なる手段と割り切るのではなく、技術への愛を持ちながら開発を進めています。チームワークも重視しており、組織としての一体感も強いので、小規模な開発組織で働きたい人や、営業やカスタマーサクセスとの距離が近い環境で仕事をしたい人にとっては、魅力的なチームだと思います。また、AIエージェントの例でも示したように、最新技術に積極的に触れたい人にとっても、挑戦しやすい環境です。
テクニカルリードの原が当社の技術ブログで執筆した「COエンジニアで働く理由」では、エンジニアとしての視点から、いまContract Oneで働くことの魅力について深く掘り下げています。
私たちの組織では「視野を広げて、プロダクトへの要求を超える」というミッションを掲げています。これは、単に与えられた要求を実装するのではなく、要求の先にある課題を理解するために多角的な情報を得る。そして、エンジニアならではの付加価値を加えたアウトプットでユーザーからの期待、プロダクトチームからの期待を超えるという意味です。エンジニアとしてプロフェッショナルでありつつ、クロスファンクショナルな働き方を推進する意図も込めています。
私自身、要求を120%達成することで、ユーザーから信頼され、プロダクトが良くなると信じています。プロダクトマネジャーにも「エンジニアに対して忖度せず、高い期待値をかけてほしい」と伝えており、それによってチーム全体がポジティブに影響を受け、高い成果を上げることができています。
山邊さんの今後のビジョンについてお聞かせください。これからエンジニアとしてどのように挑戦していきたいですか?
「Bill One」に携わっていた頃は、自然と組織が大きくなっていきましたが、自分が直接影響を与えて成長させた実感はほとんどありませんでした。そのため「Contract One」では組織の成長を実感しながら、自分が組織を大きくする意識を持って取り組んでいます。具体的には、組織拡大のためのフロー構築や受け入れ体制の整備、さらにチームの技術力を維持しながら人を増やす方法を学びたいと考えています。
また、自分自身の成長のためにも、できることを増やし、プロダクト開発において影響を与えられる範囲を広げたいですね。開発スピードを向上させていく必要もあると感じています。長期的には「自分自身で新しい何かを生み出したい」という目標があり、そのための道を進んでいる最中です。