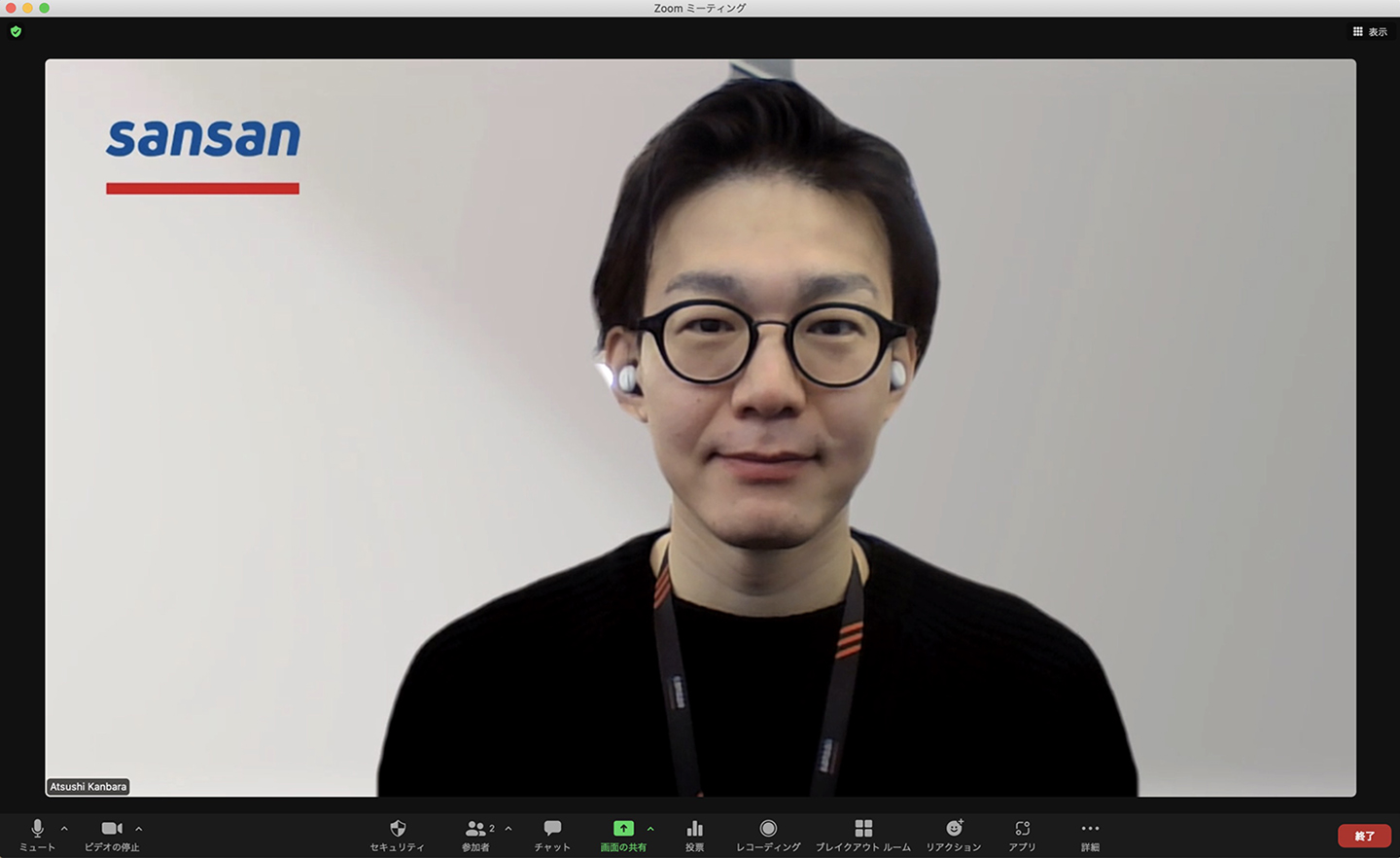こんにちは、mimi編集部です。
当社は、2021年10月に組織体制と働き方を一新したことを発表しました。それから半年が経過した現在、メンバーたちはどんな目標を掲げ、業務に向き合っているのでしょうか。
今回は、技術本部に属する3つのグループでマネジメントを務める3人にインタビュー。それぞれのグループの働き方に加え、推進しているプロダクトや組織の課題についても話を聞きました。
当社は、2021年10月に組織体制と働き方を一新したことを発表しました。それから半年が経過した現在、メンバーたちはどんな目標を掲げ、業務に向き合っているのでしょうか。
今回は、技術本部に属する3つのグループでマネジメントを務める3人にインタビュー。それぞれのグループの働き方に加え、推進しているプロダクトや組織の課題についても話を聞きました。
新しくなったSansanの働き方とは...
エンジニアやデザイナーなど、クリエイティブ職は週1日または3日の出社のどちらかを選び、セールスやマーケターといったビジネス職は週3日の出社を基準とするルール。
技術本部 データ戦略部データの力でSansanを牽引する
技術本部 データ戦略部 副部長 神原 淳史
入社年と担当している業務を教えてください
2014年に入社し、現在は技術本部の「データ戦略部」で副部長を務めています。データ戦略部をすこし抽象的に表すと、データの力でSansan株式会社を牽引するための部署です。
その中で私の役割は、副部長としてエンジニアリングのマネジメントを中心に、メンバー全員が力を発揮し、その結果がより適切に顧客価値につながるようにすることだと考えています。
「新しい働き方」でのチームの働き方や雰囲気について教えてください
週1回以上出社するメンバーと週3回以上出社するメンバーの割合は、現在ちょうど半々ぐらいですね。技術本部内の他チームよりは週3回以上出社するメンバーの割合が高めという印象です。出社するタイミングが多様になっている今、コミュニケーションの質・量ができるだけ落ちないようにするために、ツールを積極的に活用していますね。Web会議ツールはもちろんのこと、バーチャルオフィスツールやオンラインホワイトボードツール等も使っています。
具体的には、通称ザッソウ (雑な相談) を生まれやすくするために、毎日チーム朝会も実施しています。
どんなモチベーションで業務に向き合っていますか?
データ戦略部は発足したばかりなので、まだ誇れる成果があるわけではありません。ただ、私も含めチームのメンバーはこの部署のミッションにとてもワクワクしていますね。なぜなら、データの力でSansanを牽引するということは、Sansanの未来を創ることと、ニアリーイコールだと感じているからです。
Sansanのミッション「出会いからイノベーションを生み出す」という世界観のもと、ビジョンに掲げている「ビジネスインフラになる」を実現していく。そのためには、創業以来提供してきた「名刺管理」に続く第二、第三の価値創造が必要です。
データを顧客からお預かりするだけでなく、データを保有し提供するデータカンパニーになる。それが第二、第三の価値創造に繋がると信じています。
データ戦略部が抱える課題はなんですか?また、その課題解決にはどのように向き合っていますか?
Sansan株式会社が真の意味でデータカンパニーになるためには、顧客から預かる以外の形でデータを収集し、提供できる形に変換する必要があります。これは、Webに公開されている情報には限りがあるということもあって、非常に困難な課題です。
高度な技術力はもちろんのこと、技術以外の手段も駆使することで初めて実現性が出てきます。
Webクローリングと自然言語解析のような技術的なアプローチをとることもあれば、他社との協業のようなアプローチをとることもあります。このように、幅広い選択肢の中から最適な方法を見極めることが求められます。
データ戦略部のエンジニアは、そういった困難な課題に立ち向かうことが求められていると感じますね。
自チームに新たにジョインする人にはどのようなことを期待していますか?
「データの力でSansanを牽引する」この壮大なデータ戦略部のミッションに共感し、オーナーシップをもって取り組める人にジョインしていただきたいです。技術本部 Seminar One Engineering グループプロダクトをスケールさせる開発組織を構築
Seminar One Engineering グループ グループマネジャー 鈴木 康寛
入社年と担当している業務を教えてください
2013年入社後、2021年までは名刺アプリ「Eight」の開発業務を行っていました。当初はサーバーサイドエンジニアでKPI基盤の改善やフィードのプロトタイプ開発、リコメンドエンジンのサーバーレス化などを行いました。その後はEight開発チーム全体のマネジメントを行い、後に企業向けプレミアムの開発チームでプレイングマネジャーとして、現在の「Eight Team」の前身となる基盤の開発や、オプション機能の開発を推進しました。
2021年6月からは現在の「Seminar One Engineering グループ」で、グループマネジャーになりました。プロセス刷新やチームメンバーのマネジメントを行い、グループの成果の最大化を目指してマネジメント業務を行っています。
参考:エンジニアリングマネージャーの登壇実績(EOF 2019)
「新しい働き方」でのチームの働き方や雰囲気について教えてください
「技術本部 Digitization部 部長 永井 晋平
入社年と担当している業務を教えてください
2007年に入社し、Sansan が展開する多くのプロダクトの中で共通に重要となる、紙の名刺や請求書や契約書のデータ化を行っています。データ化では「精度」が何より重要です。それを実現するため、人力と技術を融合する形でデータ化にに日々向き合っています。
現在はこのデータ化を Sansan の武器とするために人による入力オペレーションを含めたデータ化の仕組みづくりと、その仕組みを実現するためのシステム開発を担う「Digitization部」でマネージャーを務めています。
「新しい働き方」でのチームの働き方や雰囲気について教えてください
Digitization部は、7割以上が週3日出社しています。この割合はエンジニアだけではなくて、オペレーションの管理を行うメンバーも所属していることにも関係しています。エンジニアだけだと週1出社と、週3出社が半々の割合です。ここは本人たちの業務ペースの作りやすさなどが反映されていると思います。
チームの働く環境づくりとしては、新型コロナウィルスが感染拡大する前から朝会を各グループ・チームで集まって実施しています。
打ち合わせなければ黙々と仕事に向き合って人と話さず終わるというのは開発者にとってあるあるだと思いますが、朝の始まりで顔を合わせてそれぞれの声を聞く機会をつくるようにしていますね。
また、月イチで部会をやっているのですが、私としてはここで部門全体の動きや数字の話、自分自身が考えていることを伝えることを大事にしています。
持っている情報で個々人の行動は変わると思うので、丁寧な情報提供というのは以前よりも意識していると思います。
組織体制、働き方のアップデート後、記憶に残る印象的なエピソードを教えてください。
もともと独立してデータ化という領域を担っていた部門なので、わかりやすく変化というものは感じづらかったと思います。ただ、このタイミングでデータ化のためのオペレーションとして、入力だけではなくスキャン業務も巻き取り統合するという大きなプロジェクトが始まったことは印象的な出来事でした。
まだ始まったばかりで乗り超えないとならない課題が山積みですが、大変チャレンジし甲斐があると思っています。
これから乗り越える困難とはどのようなものでしょうか?
「紙の情報をスキャンして画像にする」という工程はデータ化の入り口ですが、多くはユーザーに担ってもらう中で一部をSansanで代行します。名刺のスキャン、請求書のスキャン、契約書のスキャンはこれまで各プロダクトでバラバラに設計され、業務を構築してきました。
今後は入力のオペレーションに加えて、スキャンのオペレーションも統合し、ひとつの部門が担うことでより最適な業務に進化させるとともに、将来生み出される新たなアナログをデジタルにしていくプロダクトの提供を素早く構築できることを目指します。
Sansanのマルチプロダクト化を支えるという意味においては各プロダクトの要求は個別化されますし、個別化すべきポイントもあります。ただ、個別に向き合うだけでは統合のメリットは小さく、何を共通の資産として、何を個別の資産とするかの見極めはとても難しくチャレンジングです。
オペレーション統合の話は始まったばかりですが、今後の成長になくてはならないプロジェクトだと信じています。
上記の課題に対してどのように向き合っていますか?
まずは各業務を知るということからはじめていますが、その中で現在「Bill One」というプロダクトが急成長している関係で、システム開発がこれまでにないスピードで求められています。具体的には、スキャン、入力のスピード、入力の効率化や自動化、一気に増えるオペレーターのオンボーディングやアサインコントコロールなどのオペレーション全般の仕組みづくりですね。
個々人が各業務のボトルネックなどの数字やオペレーターの声に向き合って創意工夫していかなければならないことだけでもチャレンジングな状況ですが、まずは「Bill One」業務を安定的に回すためのシステムや仕組みの構築ということに向き合っています。
自チームに新たにジョインする人にはどのようなことを期待していますか?
日々、大量のデータ化やスキャンを行っていますが、一瞬で正しい情報を提供できることは利用者にとって大きな価値だと考えています。ただし、この実現方法はまだ誰も知らないですし、難題です。
データに基づいてオーナーシップを持って価値提供、ものづくりに向き合いたいと考えている方はきっと活躍いただけると考えています。
編集後記
出社頻度はグループによってさまざまですが、印象的だったのは共通してコミュニケーションの量と質を大切にしており、朝会や夕会、雑談タイムがあることでした。そして、大きな組織体制があり、完成されている会社と思われがちなSansanですが、まだまだ沢山の課題を抱えていました。一方でそれらの課題はチャレンジし甲斐のあるものでもあり、新たな仲間を求めている理由でした。
Sansanエンジニア組織の一例でしかありませんが、Sansanエンジニアのリアルを多少なりともお伝えできたのではいかと思っています。
text&photo: mimi